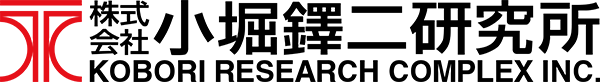- 1986年
- 株式会社 小堀鐸二研究所設立(初代代表取締役社長:小堀 鐸二 )
- 1989年
- 世界初のアクティブ制震の実用化
- 1991年
- パッシブ制震装置ハニカムダンパをシーフォートタワーに適用
- 1998年
- 各種地震動評価技術の開発と実業務への適用
- 2000年
- セミアクティブ制震装置HiDAXを中部電力岐阜支店ビルに適用
-
- 米国ブラックサンダーにて発破震動による液状化実験実施
- 2005年
- 新型セミアクティブ制震装置HiDAX-eを超高層ビルに適用
- 2007年
- 代表取締役社長に 五十殿侑弘 が就任
-
- 小堀 鐸二 逝去
- 2009年
- 日本初の風力発電設備の国土交通大臣認定取得
-
- 日本初の長周期地震動用制震改修を新宿パークタワーで実施
- 2010年
- 南海トラフ巨大地震の長周期地震動評価
- 2012年
- 東京都庁舎の長周期地震動対策としての制震改修設計
-
- 洋上風力発電設備の国土交通大臣認定取得
- 2015年
- 建物安全度判定支援システム q-NAVIGATOR の実用化
- 2016年
- q-NAVIGATOR 採用建物 累計100棟超え
- 2017年
- 代表取締役社長に 中島正愛 が就任
- 2018年
- 官民研究開発投資拡大プログラム(PRISM)に研究課題が採択
- 2019年
- 革新的社会資本整備研究開発推進事業(BRAIN)に研究課題が採択
- 2022年
- q-NAVIGATOR 採用建物 累計500棟超え